本サイトでは、二級建築士試験「建築法規」の過去問題について、どこよりも詳しく解説しています。
全て無料で公開していますので、試験合格に向けた勉強にお役立てください。
 【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
二級建築士の試験対策教材はこちらを参考にしてください。
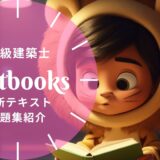 【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説!
【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説!
問題No.19【防火・準防火地域】の概要
- 法第61条~法第65条
- 令第136条の2、令第136条の2の2
建築法規の19問目で出題されるのが防火・準防火地域に関する問題です。
防火・準防火地域内にある建築物の耐火・準耐火建築物等の要求、屋根の性能や隣地境界線に接する外壁、看板等の防火措置、地域の内外にわたる場合の措置について、毎年1問出題されます。
耐火・準耐火建築物等の要求の問題では、法27条の特殊建築物の構造制限も絡めて問題が出題されますので、注意してください。
出題範囲は限られていて、パターンも毎年同じなので、必ず正答するように対策しましょう。
では早速、過去の出題のパターンから、出題傾向を見ていきましょう。
防火・準防火地域内の構造制限
防火地域内の構造制限
法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)
令第136条の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)
令和元年国交省告示第194号
防火・準防火地域内では、対象建築物の階数や延べ面積により、耐火義務など構造規制が発生します。
防火地域内の対象建築物の階数や延べ面積に応じた構造規制は、以下の表のとおりです。
| 階数 | 延べ面積 | 構造規制 |
|---|---|---|
| 2階以下 | 100㎡以下 | 耐火、準耐火建築物等 |
| 100㎡超え | 耐火建築物等 | |
| 3階以上 | すべて | 耐火建築物等 |
準防火地域内の構造制限
準防火地域内の対象建築物の階数や延べ面積に応じた、構造規制は以下の表のとおりです。
| 階数 | 延べ面積 | 構造規制 |
|---|---|---|
| 2階以下 | 500㎡以下 | 制限なし※ |
| 500㎡超え1,500㎡以下 | 耐火、準耐火建築物等 | |
| 1,500㎡超え | 耐火建築物等 | |
| 3階 | 500㎡以下 | 耐火、準耐火建築物等又は防火上必要な技術基準に適合 |
| 500㎡超え1,500㎡以下 | 耐火、準耐火建築物等 | |
| 1,500㎡超え | 耐火建築物等 | |
| 4階以上 | すべて | 耐火建築物等 |
※:木造建築物等で、外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分は、防火構造
防火・準防火地域内の構造制限から出題された過去問題
【令和5年問題】
防火地域内にある建築物に附属する高さ 2 mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
設問は、正しい。
令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
【令和4年問題】
準防火地域内において、鉄筋コンクリート造 2 階建ての一戸建て住宅に附属する高さ 2mを超える塀を設ける場合、その塀は、延焼防止上支障のない構造としなくてもよい。
設問は、正しい。
令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
設問は、鉄筋コンクリート造に附属する塀の場合のため、延焼防止上支障のない構造としなくてもよい。
【令和3年問題】
準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。
設問は、正しい。
令第136条の2第三号イより、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のもの(木造建築物等に限る。)は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。
【令和3年問題】
準防火地域内において建築物に附属する高さ 2 mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
設問は、誤っている。
令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
【令和2年問題】
防火地域内にある建築物に附属する高さ 2 mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
設問は、正しい。
令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
【平成30年問題】
準防火地域内にある木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ることができる。
設問は、正しい。
令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造であること。
【平成29年問題】
防火地域内において、3階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。
設問は、正しい。
法第61条ただし書きより、防火地域内において、高さ2m以下の門又は塀は、木造とすることができる。
【平成29年問題】
準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
設問は、誤っている。
令第136条の2第三号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のもの(木造建築物等に限る。)は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
防火・準防火地域内の特殊建築物の構造制限
法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
法別表第1(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
防火・準防火地域内の特殊建築物の構造制限は、法第61条による防火・準防火地域による制限と併せて、法第27条による用途による制限も確認を行い、厳しい方の制限を受けます。
耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物は、以下の表のとおりです。
| 用途 | 耐火建築物とする | 耐火又は準耐火建築物とする | |
|---|---|---|---|
| 用途のある階 | 用途の床面積の合計 | 用途の床面積の合計 | |
| 劇場、映画館、演劇場 | 主階が1階にないもの | 200㎡以上(客席の部分) (屋外観覧席1,000㎡以上) | ー |
| 3階以上の階 | |||
| 観覧場、公会堂、集会場 | 3階以上の階 | ||
| 病院、診療所(有床)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 | 3階以上の階 | ー | 300㎡以上(2階の部分(病院、診療所は2階に病室があるもの)) |
| 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、水泳場、スポーツ練習場 | 3階以上の階 | ー | 2,000㎡以上 |
| 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物販店 | 3階以上の階 | 3,000㎡以上 | 500㎡以上(2階の部分) |
| 倉庫 | ー | 200㎡以上(3階以上の部分) | 1,500㎡以上 |
| 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ | 3階以上の階 | ー | 150㎡以上 |
| 危険物の貯蔵場又は処理場(令116条表) | ー | ー | 全て |
防火・準防火地域内の特殊建築物の構造制限から出題された過去問題
【令和2年問題】
準防火地域内にある 3 階建て、延べ面積 300㎡の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。
設問は、誤っている。
法第27条及び法別表第1(い)欄(2)項より、診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなくてもよい。
令第136条の2第一号より、準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が4以上のもの若しくは延べ面積が1,500㎡を超えるものでないため、耐火建築物としなくてもよい。
【令和元年問題】
準防火地域内の建築物で、 3 階をテレビスタジオの用途に供するものを新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
設問は、正しい。
法第27条第2項第二号、法別表第1(6)項及び令第115条の3第四号より、 3 階をテレビスタジオの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない特殊建築物である。
【平成30年問題】
準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
設問は、誤っている。
令第136条の2第二号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のもの若しくは地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下のものは、耐火建築物及び準耐火建築物としなければならない。
【平成29年問題】
準防火地域内において、2階建て、延べ面積 300㎡(客席の床面積 200㎡)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。
設問は、正しい。
客席の床面積 200㎡の集会場は、法第27条第1項第二号に該当すため、令第110条より、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。
また、法第61条及び令第136条の2より、準防火地域内の建築物として耐火建築物とする必要はない。
防火・準防火地域内のその他の構造制限
屋根の構造
法第62条(屋根)
令第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能は、以下の表のとおりです。
| 地域 | 建築物の用途 | 必要な性能 |
|---|---|---|
| 防火地域 準防火地域 | すべて(下記以外) | 非発炎性 非損傷性 |
| 不燃性物品の倉庫等 | 非発炎性 |
屋根の構造から出題された過去問題
【令和5年問題】
防火地域内において、共同住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。
法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
【令和4年問題】
準防火地域内において、一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。
法第62条(屋根)及び令第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
【令和3年問題】
準防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。
法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
【令和2年問題】
防火地域内において一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。
法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
【令和元年問題】
防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。
法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
隣地境界線に接する外壁
法第63条(隣地境界線に接する外壁)
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
隣地境界線に接する外壁から出題された過去問題
【令和5年問題】
防火地域内の建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、正しい。
法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
【令和4年問題】
準防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、誤っている。
法第63条(隣地境界線に接する外壁)より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、準耐火構造のため、誤っている。
【令和3年問題】
防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、正しい。
法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
【令和元年問題】
準防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、誤っている。
法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。設問は、準耐火構造のため、誤っている。
【平成30年問題】
防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、誤っている。
法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。設問は、準耐火構造のため、誤っている。
看板等の防火措置
法第64条(看板等の防火措置)
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔などで、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
| 地域 | 防火地域内 |
| 工作物 | 看板、広告塔、装飾塔など |
| 設置場所、規模 | 建築物の屋上に設置、高さ3mを超えるもの |
| 構造制限 | 主要な部分を不燃材料で造るか、又は覆う |
看板等の防火措置から出題された過去問題
【令和5年問題】
防火地域内において、地上に設ける高さ 3.5 mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。
法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
【令和4年問題】
防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。
法第64条(看板等の防火措置)より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
【令和2年問題】
防火地域内の高さ 2 mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。
法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
【令和元年問題】
防火地域内の高さ 2 mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。
法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
【平成30年問題】
防火地域内にある高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。
法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
【平成29年問題】
防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。
法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
防火・準防火地域の内外にわたる場合
法第65条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
建築物が2つの地域の内外にわたる場合、防火壁で区画されている場合を除き、建築物全体について厳しい方の制限を受けます。
防火・準防火地域の内外にわたる場合から出題された過去問題
【令和5年問題】
建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物であっても、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
設問は、誤っている。
法第65条より、建築物が2つの地域の内外にわたる場合、防火壁で区画されている場合を除き、建築物全体について厳しい方の制限を受ける。
設問は、敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物であり、建築物が2つの地域の内外にわたっていないため、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
【令和4年問題】
敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物には、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
設問は、正しい。
法第65条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)より、建築物が2つの地域の内外にわたる場合、防火壁で区画されている場合を除き、建築物全体について厳しい方の制限を受ける。
設問は、敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物であり、建築物が2つの地域の内外にわたっていないため、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
【令和3年問題】
建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
設問は、正しい。
法第65条第1項より、建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
【令和2年問題】
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
設問は、正しい。
法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
【令和元年問題】
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
設問は、正しい。
法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
【平成30年問題】
防火地域及び準防火地域にわたり、2階建て、延べ面積110㎡の一戸建て住宅を新築する場合、耐火建築物としなければならない。
設問は、正しい。
法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物としなければならない。
【平成29年問題】
木造2階建て、延べ面積 200㎡の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。
設問は、正しい。
法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物としなければならない。
問題No.19【防火・準防火地域】のまとめ
建築法規の19問目では、防火・準防火地域内にある建築物の耐火・準耐火建築物等の要求、屋根の性能や隣地境界線に接する外壁、看板等の防火措置、地域の内外にわたる場合の措置について、出題されます。
 【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
二級建築士の試験対策教材はこちらを参考にしてください。
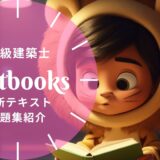 【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説!
【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説! 



