本サイトでは、二級建築士試験「建築法規」の過去問題について、どこよりも詳しく解説しています。
全て無料で公開していますので、試験合格に向けた勉強にお役立てください。
 【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
二級建築士の試験対策教材はこちらを参考にしてください。
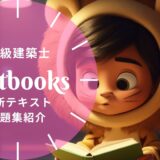 【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説!
【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説!
- 法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
- 法別表第1(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
- 令第5章 避難施設等
(令第116条の2~令第128条の3)
建築法規の10問目で出題されるのが令第5章の避難施設等の問題です。
避難施設等に定められている廊下幅、歩行距離、排煙設備、非常用照明、敷地内通路等から、五肢択一式の問題で毎年必ず1問出題されます。
令第121条「2以上の直通階段」の規定は、用途と規模で対象建築物を判断するのに時間を要するため、他の設問から優先して特のも対策の1つです。ただ、出題頻度は高いため、対策はしっかりしておきましょう。
廊下・避難階段及び出入口
適用の範囲

令第117条(適用の範囲)
第5章第2節(廊下、避難階段及び出入口)の規定の適用範囲は、令第117条(適用の範囲)~令第126条(屋上広場等)です。
適用される対象建築物の範囲は、以下のとおりです。
- 特殊建築物
(法別表1(い)欄(1)~(4)までの用途) - 階数が3階以上
- 無窓居室を有する建築物
(採光面積<居室床面積の1/20) - 延面積1,000㎡超の建築物
(同一敷地内に2棟以上ある場合は、その延面積の合計)
| 1 | 法別表1(い)欄(1)~(4)までの用途の特殊建築物 |
| (1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | |
| (2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 | |
| (3)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 | |
| (4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) | |
| 2 | 階数が3以上の建築物 |
| 3 | 採光上無窓の居室を有する建築物 採光有効面積が居室の床面積の1/20以上の窓その他の開口部を持たない居室のある階 |
| 4 | 延べ面積が1,000㎡を超える建築物 |
客席からの出口の戸
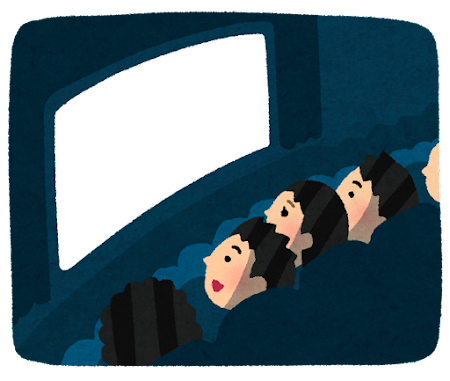
令第118条(客席からの出口の戸)
対象建築物の用途は、不特定多数(集中)のものは、避難するときに出入り口に人が一気に集中します。
避難の際に、客席からの出口が詰まると大きな混乱が生じることから、内開きとしてはならない規定が定められています。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
客席からの出口の戸から出題された過去問題
【令和4年問題】
集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
設問は、正しい。
令第118条より、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
廊下の幅

令第119条(廊下の幅)
廊下の用途ごとの廊下幅は、以下のとおりです。
| 用途\廊下の配置 | 両側居室 | 片側居室 |
|---|---|---|
| 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの | 2.3m以上 | 1.8m以上 |
| 病院における患者用のもの | 1.6m以上 | 1.2m以上 |
| 共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの | ||
| 3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡を超える階におけるもの(地階にあつては、100㎡) |
廊下の用途
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの
両側に居室がある廊下:2.3m以上
その他の廊下:1.8m以上
廊下の用途
- 病院における患者用のもの
- 共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計>100㎡の階の共用のもの
- 居室の床面積の合計>200㎡の階(地階100㎡)(3室以下の専用のものを除く)
両側に居室がある廊下:1.6m以上
その他の廊下:1.2m以上
廊下の幅から出題された過去問題
【令和5年問題】
小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。
設問は、誤っている。
令第119条より、小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。
【令和4年問題】
木造 2 階建て、延べ面積 100㎡の一戸建ての住宅においては、廊下の幅に制限はない。
設問は、正しい。
令第117条第1項より、廊下幅の規定は、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000㎡をこえる建築物に限り適用する。
また、令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階であっても、令第119条より、3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるものが制限を受ける。
よって、木造 2 階建て、延べ面積 100㎡の一戸建ての住宅においては、廊下の幅に制限はない。
【令和2年問題】
病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。
設問は、正しい。
令第119条の表より、病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。
【平成30年問題】
小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。
設問は、正しい。
令第119条より、小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。
直通階段の設置

令第120条(直通階段の設置)
建築物の避難階以外の階は、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離が定められています。
居室の種類ごとの直通階段までの歩行距離は、以下のとおりです。
居室の種類
採光上の無窓居室
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物販店舗(床面積≦10㎡除く)
準耐火構造又は不燃材料:30m以下
上記以外:30m以下
居室の種類
病院、診療所(有床)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
準耐火構造又は不燃材料:50m以下
上記以外:30m以下
居室の種類
①又は②に掲げる居室以外の居室
準耐火構造又は不燃材料:50m以下
上記以外:40m以下
以下の該当する場合、歩行距離の加算や低減を行います。
- 主要構造部が準耐火構造又は不燃材料でつくられ、居室及び通路の内装を準不燃材料でしたものは、歩行距離の限度を10m加算する。
- 15階以上の階の居室は、歩行距離の限度を10m低減する。
直通階段の設置から出題された過去問題
【令和4年問題】
木造 2 階建ての一戸建て住宅においては、 2 階の居室の各部分から 1 階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離の制限を受けない。
設問は、誤っている。
令第117条第1項より、令第120条の規定は、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000㎡をこえる建築物に限り適用する。
令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階である場合、木造 2 階建ての一戸建て住宅においては、 2 階の居室の各部分から 1 階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離の制限を受ける。
【令和3年問題】
木造 2 階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積 600 m(各階の床面積 300㎡、 2 階の居室の床面積 250㎡)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は 1 階とする。
2 階の居室の各部分から 1 階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30 m以下としなければならない。
設問は、正しい。
令第115条の3より、物品販売業を営む店舗は法別表第1(い)欄(4)項に該当する。令第120条第1項の表より、法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室の各部分から 1 階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30 m以下としなければならない。
【令和2年問題】
主要構造部を準耐火構造とした 2 階建ての有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を 60 m以下としなければならない。
設問は、正しい。
令第120条第1項の表より、主要構造部を準耐火構造とした 有料老人ホームの避難階以外の階においては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を 50 m以下となる。
また、同条2項より、主要構造部が準耐火構造とした建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、10を加えた数値を同項の表の数値とする。
よって、歩行距離は、50m+10m=60m以下としなければならない。
【平成29年問題】
2階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を 60m以下としなければならない。
設問は、正しい。
令第115条の3第一号より、幼保連携型認定こども園は、法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物である。
令第120条第1項表(2)より、耐火建築物である幼保連携型認定こども園の表の数値は50mである。
また、同条第2項より、耐火建築物の居室で、居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、表の数値に10mを加える。
よって、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、50m+10m= 60m以下としなければならない。
2以上の直通階段を設ける場合

令第121条(2以上の直通階段を設ける場合)
建築物の避難階以外の階が次のいずれかに該当する場合は、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 対象用途 ①劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物販店舗(床面積の合計1,500㎡超えのもの)
客席、集会室、売場その他これらに類するものを有する階 - 対象用途 ②キャバレー等
客席、客室その他これらに類するものを有する階 - 対象用途 ③病院、診療所、児童福祉施設等
床面積50㎡超えの病室、主たる用途に供する居室を有する階※ - 対象用途 ④ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
床面積100㎡超えの宿泊室、居室、寝室を有する階※ - 対象用途 ⑤①~④以外の用途
居室を有する下記の階- 居室を有する6階以上の階
- 床面積200㎡超えの居室を有する5階以下の階(避難階の直上階)※
- 床面積100㎡超えの居室を有する5階以下の階(その他の階)※
※主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の場合、床面積の数値は以下とします。
「50㎡」→「100㎡」
「100㎡」→「200㎡」
「200㎡」→「400㎡」
| 建築物の用途 | 床面積の合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 主要構造部が準耐火構造又は不燃材料 | ||||
| ① | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物販店舗(床面積の合計1,500㎡超えのもの) | すべて | すべて | ||
| ② | キャバレー等 | すべて | すべて | ||
| ③ | 病院、診療所、児童福祉施設等 | 50㎡超 | 100㎡超 | ||
| ④ | ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎 | 100㎡超 | 200㎡超 | ||
| ⑤ | 上記以外 | 居室を有する6階以上の階 | すべて | すべて | |
| 5階以下の階 | 避難階の直上階 | 200㎡超 | 400㎡超 | ||
| その他の階 | 100㎡超 | 200㎡超 | |||
2以上の直通階段から出題された過去問題
【令和5年問題】
特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
設問は、誤っている。
令第121条第1項第六号より、6階以上の階でその階に居室を有するものや、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200㎡を、その他の階にあつては100㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならない。
【令和3年問題】
木造 2 階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積 600 m(各階の床面積 300㎡、 2 階の居室の床面積 250㎡)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は 1 階とする。
2 階から 1 階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第121条第1項第六号ロより、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200㎡を、その他の階にあつては100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。しかし、同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、「200㎡」とあるのは「400㎡」とする。
計画の建物は、主要構造部を準耐火構造としたもので、2 階の居室の床面積 250㎡であることから、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい。
【令和2年問題】
2 階建て、各階の床面積がそれぞれ 200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は 1 階)は、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第121条第1項各号より、2 階建て、各階の床面積がそれぞれ 200㎡の物品販売業を営む店舗は、該当しないため、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなくてもよい。
【令和元年問題】
次の 2 階建ての建築物(各階を当該用途に供するものとし、避難階は 1 階とする。)のうち、建築基準法上、 2 以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。
共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、 2 階の居室の床面積の合計が 150㎡のもの
設問は、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい。
令第121条第1項第五号より、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。しかし、同条第2項より、主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、「100㎡」とあるのは「200㎡」とする。
【令和元年問題】
次の 2 階建ての建築物(各階を当該用途に供するものとし、避難階は 1 階とする。)のうち、建築基準法上、 2 以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。
診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、 2 階の病室の床面積の合計が100㎡のもの
設問は、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい。
令第121条第1項第四号より、診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計が、それぞれ50㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。しかし、同条第2項より、主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、「50㎡」とあるのは「100㎡」とする。
【令和元年問題】
次の 2 階建ての建築物(各階を当該用途に供するものとし、避難階は 1 階とする。)のうち、建築基準法上、 2 以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。
事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ 180㎡のもの
設問は、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい。
令第121条第1項第六号ロより、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200㎡を、その他の階にあつては100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。
【令和元年問題】
次の 2 階建ての建築物(各階を当該用途に供するものとし、避難階は 1 階とする。)のうち、建築基準法上、 2 以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。
飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、 2 階の居室の床面積の合計が 150㎡のもの
設問は、2 以上の直通階段を設けなけなくてよい。
令第121条第1項第六号ロより、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200㎡を、その他の階にあつては100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。
【令和元年問題】
次の 2 階建ての建築物(各階を当該用途に供するものとし、避難階は 1 階とする。)のうち、建築基準法上、 2 以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。
寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、 2 階の寝室の床面積の合計が 120㎡のもの
設問は、2 以上の直通階段を設けなければならない。
令第121条第1項第五号より、寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるものは、2 以上の直通階段を設けなければならない。
【平成30年問題】
避難階が1階である2階建ての下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、2階における宿泊室の床面積の合計が200㎡であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第121条第1項第五号より、ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
令121条2項より、主要構造部が不燃材料で造られている建築物は、「100㎡」とあるのは「200㎡」とする。設問は、200㎡を超えていないため誤っている。
【平成29年問題】
避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が 250㎡のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、正しい。
令第121条第1項第五号より、ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
避難階段、特別避難階段の設置
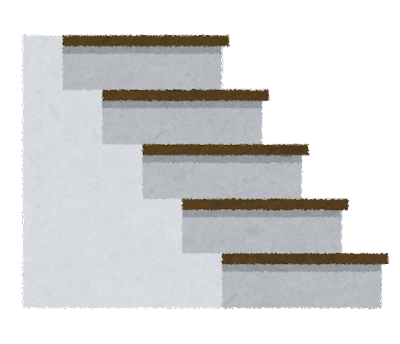
令第122条(避難階段の設置)
建築物の用途及び階数に応じ、以下のとおり避難階段又は特別避難階段の設置が必要です。
| 直通階段 | 避難階段の種類 | |
|---|---|---|
| 物販店舗(床面積合計が1,500㎡超) | 15階以上の階に通じる直通階段 | すべてを特別避難階段 |
| 5階以上の階に通じる直通階段 | 1以上を特別避難階段 | |
| 3以上の階で各階の売場及び屋上に通じるもの (2以上の直通階段を設ける) | 避難階段または特別避難階段 | |
| 一般建築物 | 15階以上の階に通じる直通階段 | 特別避難階段 |
| 地下3階以下に通じる直通階段 | ||
| 5階以上の階に通じる直通階段 | 避難階段または特別避難階段 | |
| 地下2階以下に通じる直通階段 |
3階以上にある床面積の合計が1,500㎡超えの物販店舗
- 15階以上の階に通じる直通階段
特別避難階段 - 5階以上の階に通じる直通階段
避難階段又は特別避難階段※1 - 3階以上の階で各階の売場及び屋上広場に通じる直通階段
避難階段又は特別避難階段※2
※1:1箇所以上を特別避難階段としなければならない。
※2:2以上の直通階段を設けなければならない。
上記以外の建築物(除外規定あり※3)
- 15階以上の階、地下3階以下に通じる直通階段
特別避難階段 - 5階以上の階、地下2階以下に通じる直通階段
避難階段又は特別避難階段
※3:除外規定
- 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階又は地下2階以下の階の床面積の合計が100㎡以下である場合
- 主要構造部が耐火構造である建築物で床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸は、200㎡)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2㎡以下のものに設けられる防火設備を含む。)で区画されている場合
- (階段室の部分、昇降機の昇降路の部分及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)
避難階段及び特別避難階段の構造
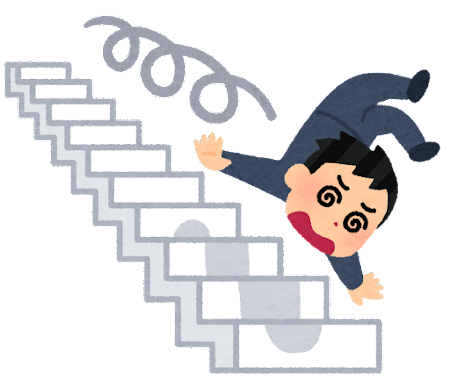
令第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)
避難階段は、「屋内に設ける避難階段」「屋外に設ける避難階段」「特別避難階段」の種類に応じて構造が定められています。それぞれの避難階段の構造は以下のとおりです。
- 階段室は、耐火構造の壁で囲む(4の開口部、5の窓又は6の出入口の部分を除く)
- 階段室の内装は、天井・壁は、下地、仕上げとも不燃材料で造る
- 採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設ける
- 屋外に面する開口部は、階段室以外の開口部から90㎝以上離すか、50㎝以上突出したそで壁・ひさし等を設ける(開口面積が1㎡以内で、防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く)
- 屋内に面して窓を設ける場合は、その面積は1㎡以内とし、防火設備ではめごろし戸であるものを設ける
- 階段に通ずる出入口の防火設備は、常時閉鎖式防火戸又は随時閉鎖できる煙感知器又は熱煙複合式感知器連動の自動閉鎖かつ、直接手で避難の方向に開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸
- 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること
- 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2m以上の距離に設ける
(開口面積が1㎡以内で、防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く) - 屋内から階段に通ずる出入口の防火設備は、常時閉鎖式防火戸又は随時閉鎖できる煙感知器又は熱煙複合式感知器連動の自動閉鎖かつ、直接手で避難の方向に開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸
- 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること
- 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること
- 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造は、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする
- 階段室、バルコニー及び付室は、耐火構造の壁で囲むこと。
(6の開口部、8の窓又は10の出入口の部分を除く) - 階段室及び付室の内装は、天井・壁は、下地、仕上げとも不燃材料で造る
- 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設ける
- 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部は、階段室、バルコニー又は付室以外の開口部から90㎝以上離すか、50㎝以上突出したそで壁・ひさし等を設ける。また、延焼のおそれのある部分には設けないこと
- 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと
- 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること
- バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと
- 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には防火設備を設けること。
(特定防火設備及び防火設備は、常時閉鎖式防火戸又は随時閉鎖できる煙感知器又は熱煙複合式感知器連動の自動閉鎖かつ、直接手で避難の方向に開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸) - 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること
- 15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積の合計は、その階に設ける各居室の床面積に、
法別表1(い)欄(1)又は(4)に掲げる用途に供する居室にあつては8/100を乗じたものの合計以上、
その他の居室にあつては3/100を乗じたものの合計以上
避難階段及び特別避難階段の構造から出題された過去問題
【平成29年問題】
屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
設問は、正しい。
令第123条第1項第二号より、屋内に設ける避難階段は、階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅

令第124条(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)
物品販売業を営む店舗(床面積の合計1,500㎡超え)の避難階段、特別避難階段の階段の幅及びこれらに通ずる出入口の幅は、以下のとおりです。
物品販売業を営む店舗における階段の幅の合計は、その階の直上階以上の階(地階にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積/100㎡×60㎝以上
物品販売業を営む店舗における出入口の幅の合計は、地上階と地階でそれぞれに定められています。
- 地上階
その階の床面積/100㎡×27㎝以上 - 地階
その階の床面積/100㎡×36㎝以上
屋外への出口

令第125条(屋外への出口)
屋外への出口にかかる規定は、以下のとおりです。
避難階の歩行距離(令125条1項)
避難階では、
- 階段から屋外への出口までの歩行距離は、令120条に規定する数値以下とします。
- 居室の各部分から屋外への出口までの歩行距離は、令120条に規定する数値の2倍以下(避難上有効な開口部を有するものを除く。)
客用の屋外への出口の戸(令125条2項)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用の屋外への出口の戸は、内開きとしない。
屋外への出口の幅の合計(令125条3項)
物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積/100㎡×60㎝以上とする。
屋外への出口から出題された過去問題
【令和5年問題】
寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。
設問は、誤っている。
令125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は令第120条に規定する数値以下としなければならない。
寄宿舎は、法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物であり、令第120条第1項表(2)より、歩行距離の制限が定められています。
【平成29年問題】
集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。
設問は、正しい。
令第125条第2項より、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
屋上広場等

令第126条(屋上広場等)
屋上広場等にかかる規定は、以下のとおりです。
手すり壁等
屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設置
屋上広場
5階以上の階を百貨店の売場とする場合は、避難の用に屋上広場を設置
屋上広場等から出題された過去問題
【令和4年問題】
木造 2 階建ての一戸建て住宅において、 2 階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが 1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
設問は、正しい。
令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
【平成30年問題】
共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁等を設けなければならない。
設問は、正しい。
令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
排煙設備
排煙設備の設置

令第126条の2(設置)
排煙設備の設置が求められる対象建築物や対象部分が定められています。
対象建築物ごとの設置が必要になる延べ床面積は、以下のとおりです。
| 対象建築物・対象部分 | 設置が必要になる建築物の延床面積 |
|---|---|
| 特殊建築物 (法別表1(い)欄(1)~(4)までの用途) | 500㎡超 |
| 階数が3以上の建築物 | 500㎡超 |
| 排煙上の無窓居室 | 全て |
| 200㎡以上の居室部分 | 1,000㎡超 |
排煙設備の設置を要しない場合
また、令第126条の2(設置)第1項ただし書き各号では、排煙設備の設置を要しない場合が定められています。
対象建築物ごとの排煙設備の除外条件は、以下のとおりです。
| 対象建築物・対象部分 | 除外のための条件 |
|---|---|
| 病院、診療所(有床)、ホテル、旅館、寄宿舎、児童福祉施設等 | 準耐火構造の床、壁、防火設備で100㎡以下で区画された部分 |
| 共同住宅の住戸 | 準耐火構造の床、壁、防火設備で200㎡以下で区画された部分 |
| 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 | すべて |
| 階段、昇降機の昇降路 | すべて |
| 主要構造部が不燃材料の機械製作工場、不燃物保管倉庫、その他同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの | すべて |
| その他 | 天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して大臣が定めるもの |
排煙設備の構造

令第126条の3(構造)
排煙設備の構造は、以下のとおりです。
| 項目 | 構造基準 | |
|---|---|---|
| 防煙区画 | 区画面積 | 床面積500㎡以内ごとに区画 |
| 排煙口 | 位置 | 防煙区画部分の各部分から水平距離が30㎝以下となるよう設置 天井から80㎝以内を有効部分 |
| 材料 | 不燃材料で造る | |
| 構造 | 閉鎖状態を保持 手動開放装置を設ける | |
| 手動開放装置 | 手で操作する部分 | 壁に設ける場合、床面から80㎝以上1.5m以下 天井から吊り下げて設ける場合、床面からおおむね1.8m |
| 表示 | 見やすい方法でその使用方法を表示 | |
| 排煙風道 | 構造 | 建築物に設ける煙突の構造(令115条1項3号)に定める構造 |
| 防煙壁を貫通部 | 風道と防煙壁とのすき間をモルタル等、不燃材料で埋める | |
| 排煙機 | 設置が必要な場合 | 排煙口の開口面積が防煙区画部分の床面積の1/50未満 排煙口が直接外気に接しない |
| 能力 | 排煙口の開放に伴い自動的に作動 排煙容量は、120㎡/分以上 防煙区画部分の床面積1㎡につき1㎥以上 | |
| その他 | 予備電源 | 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設ける |
| 中央管理室 | 高さ31m超えで非常用エレベーターのある建築物 各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街 | |
排煙設備から出題された過去問題
【令和5年問題】
中学校における建築基準法施行令第 116 条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第126条の2第1項第二号より、学校は排煙設備を設けなくてもよい。
【令和3年問題】
木造 2 階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積 600 m(各階の床面積 300㎡、 2 階の居室の床面積 250㎡)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は 1 階とする。
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第126条の2第1項第五号より、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。
【令和2年問題】
体育館における建築基準法施行令第 116 条の2第1 項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第126条の2第1項第二号より、体育館は排煙設備を設けなくてもよい。
非常用の照明装置
非常用の照明装置の設置

令第126条の4(設置)
非常用照明の設置基準は、以下のとおりです。
対象建築物
- 特殊建築物
(法別表1(い)欄(1)~(4)までの用途) - 階数が3以上で延面積500㎡超の建築物
- 無窓居室
(採光面積<居室床面積の1/20) - 延面積1,000㎡超の建築物
(同一敷地内に2棟以上ある場合は、その延面積の合計)
対象部分
- 居室
- 居室から地上に通ずる通路
- 上記に類する部分
(廊下接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常非常用照明を設置する場所)
除外される建築物又は部分
非常用照明を設置が求められない部分の以下のとおりです。
- 戸建て住宅、長屋、共同住宅の住戸
- 病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、その他類する居室
- 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
- 採光上有効に解放された廊下、通路等
- 無人工場や倉庫、電気室、機械室等、同一階に居室がない場合の廊下
- 避難階、その直上、直下階の居室で避難上支障がないもの
非常用の照明装置の構造
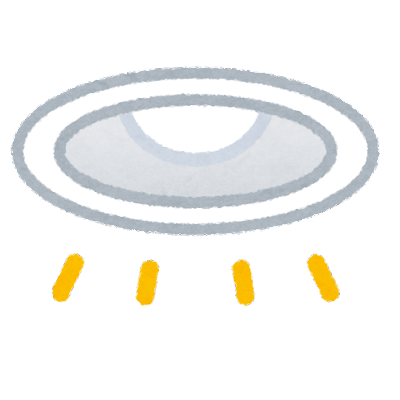
令第126条の5(構造)
非常用照明の構造基準は、以下のとおりです。
照度
直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保する。
照明器具
火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとする。
電源
予備電源を設ける。
その他
非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして大臣が定めた構造方法を用いるものとする。
非常用の照明装置から出題された過去問題
【令和5年問題】
共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第126条の4第一号より、共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設けなくてもよい。
【令和4年問題】
集会場に設置する非常用の照明装置には、予備電源を設けなければならない。
設問は、正しい。
令第126条の5第一号ハより、非常用の照明装置には、予備電源を設けなければならない。
【令和3年問題】
木造 2 階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積 600 m(各階の床面積 300㎡、 2 階の居室の床面積 250㎡)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は 1 階とする。
居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第126条の4第より、居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
【令和2年問題】
3 階建て、延べ面積 600㎡の下宿の宿泊室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第126条の4より、採光上有効に直接外気に開放された通路は、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
【平成30年問題】
飲食店の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第126条の4より、居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
非常用の進入口
非常用の進入口の設置
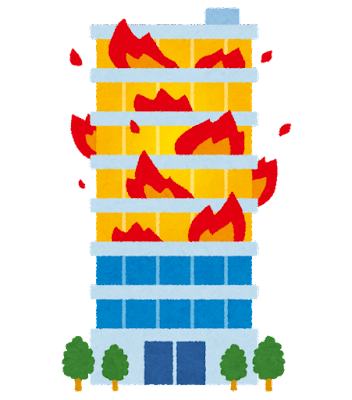
令第126条の6(設置)
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口の設置しなければならないと定められています。
また、ただし書き各号より、設置を要しない場合が定められています。
- 不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階(その直上階又は直下階から進入することができるもの
- 大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階(その直上階又は直下階から進入することができるもの
- 非常用のエレベーターを設置している場合
- 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に「進入口に代わる窓」を10m以内ごとに設けている場合
- (進入口に代わる窓は、直径1m以上の円が内接することができるもの又は幅75㎝以上、高さ1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないもの)
- 吹抜き部分等で一定の規模以上の空間で大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、高い開放性を有するものとして、大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたものを設けている場合
非常用の進入口の構造
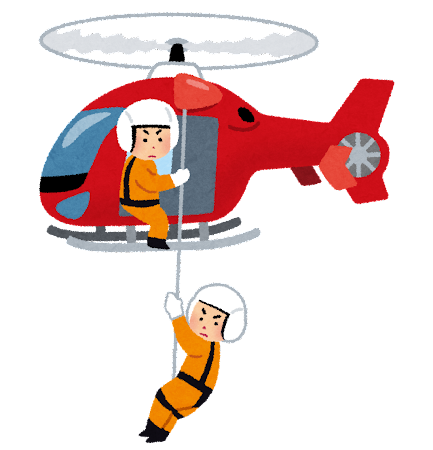
令第126条の7(構造)
非常用の進入口の構造基準は、以下のとおりです。
進入口の設置箇所
進入口の設置箇所は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設ける。
進入口の間隔
進入口の間隔は、40m以下とする。
進入口の大きさ
進入口の幅75㎝以上、高さ1.2m以上及び床面から下端までの高さ80㎝以下とする。
外部から開放又は破壊して室内に進入できる構造とする。
バルコニー
進入口には、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けること。
標識
標識は、進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示、非常用の進入口である旨を赤色で表示する。
非常用の進入口から出題された過去問題
【平成30年問題】
建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
設問は、正しい。
令第126条の7第二号より、建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
【平成29年問題】
非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第126条の6第一号より、第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてもよい。
第129条の13の3の規定に適合するエレベーターとは、非常用エレベーターである。
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
適用の範囲

- 法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
- 令第127条(適用の範囲)
第5章第6節(敷地内の避難上及び消火上必要な通路等)は、令第127条(適用の範囲)~令第128条の3(地下街)です。
適用される対象建築物の範囲は、以下のとおりです。
- 特殊建築物
(法別表1(い)欄(1)~(4)までの用途) - 階数が3階以上
- 無窓居室を有する建築物
(採光面積<居室床面積の1/20)
(排煙面積<居室床面積の1/50) - 延面積1,000㎡超の建築物
(同一敷地内に2棟以上ある場合は、その延面積の合計)
| 1 | 法別表1(い)欄(1)~(4)までの用途の特殊建築物 |
| (1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | |
| (2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 | |
| (3)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 | |
| (4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) | |
| 2 | 階数が3以上の建築物 |
| 3 | 採光上無窓の居室を有する建築物 採光有効面積が居室の床面積の1/20以上の窓その他の開口部を持たない居室のある階 排煙有効面積が居室の床面積の1/50以上の窓その他の開口部を持たない居室のある階 |
| 4 | 延べ面積が1,000㎡を超える建築物 |
敷地内の通路

令第128条(敷地内の通路)
対象通路
敷地内通路の規定の対象は、屋外避難階段及び避難階の出口から道、公園、広場、その他空地へ通ずる通路
通路幅
通路幅は、1.5m以上とする。(階数が3以下で延面積が200㎡未満の場合は、90㎝以上)
敷地内の通路から出題された過去問題
【令和3年問題】
木造 2 階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積 600 m(各階の床面積 300㎡、 2 階の居室の床面積 250㎡)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は 1 階とする。
敷地内には、建築基準法施行令第 125 条第 1 項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が 1.5 m以上の通路を設けなければならない。
設問は、正しい。
令第128条より、敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90㎝)以上の通路を設けなければならない。
問題No.10【避難施設等】のまとめ
避難施設等からの問題は、令第5章(令第116条の2~令第128条の3)の範囲から、まんべんなく問題が出題されています。
- 廊下・避難階段及び出入口
- 排煙設備
- 非常用の照明装置
- 非常用の進入口
- 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
 【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
二級建築士の試験対策教材はこちらを参考にしてください。
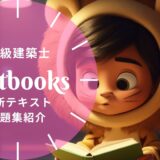 【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説!
【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説! 



