本サイトでは、二級建築士試験「建築法規」の過去問題について、どこよりも詳しく解説しています。
全て無料で公開していますので、試験合格に向けた勉強にお役立てください。
 【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
二級建築士の試験対策教材はこちらを参考にしてください。
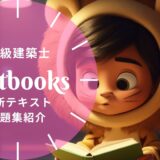 【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説!
【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説!
- 法第41条の2~法第45条
- 令第144条の4、令第145条
建築法規の12問目で出題されるのが、道路等に関する問題です。
法42条の道路の定義と法43条の敷地等と道路との関係からの問題がほとんどです。
特に道路の種類に関する問題の出題頻度が高いため、建築基準法上の道路の種類とその条件を整理しておきましょう。
その他にも、道路内の建築制限や位置指定道路に関する基準、壁面線に関しても出題されるので確認をしておきましょう。
道路の規定
適用区域

法第41条の2(適用区域)
道路等の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用します。
適用の範囲から出題された過去問題
【平成29年問題】
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。
設問は、正しい。
法第41条の2より、道路等の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
道路の定義と種類
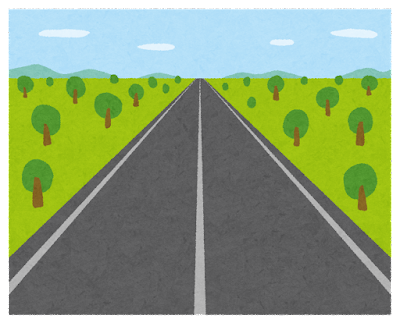
法第42条(道路の定義)
道路とは、以下の道路の種類に該当する幅員4m以上のものをいいます。
※特定行政庁が指定する区域内においては、6m以上のもの
※地下におけるものを除きます。
| 法42条各項の道路の種類 | |
|---|---|
| 1項1号道路 | 道路法による道路(国道、県道、市町村道など) |
| 1項2号道路 (開発許可道路) | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等により築造された道路 |
| 1項3号道路 (既存道路) | 建築基準法施行時に既に存在した道路 |
| 1項4号道路 (計画道路) | 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等により2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路 |
| 1項5号道路 (位置指定道路) | 政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置指定を受けたもの |
| 2項道路 (みなし道路) | 建築基準法施行時に既に建物が建ち並んでいた幅員4m(6m未満)の道で、特定行政庁が指定したもの |
| 3項道路 | 土地の状況により将来的に拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線より1.35m以上2m(3m)未満に緩和を指定したもの がけ地などは2.7m以上4m(6m)未満 |
| 4項道路 | 特定行政庁が次の各号の1に該当すると認めて指定した6m区域内の道 1号:周辺の状況により、避難・通行の安全上支障がないと認められた道 2号:地区計画等により定められ、築造される道 3号:6mの区域指定時に既に道路とされていた道 |
| 5項道路 | 6m区域指定時に既に存在していた道(4項3号)で、幅員4m未満の道は指定時に境界線とみなされていた線を境界線とする |
| 6項道路 | 建築審査会の同意を得た、幅員1.8m未満の2項道路 |
道路の定義と種類から出題された過去問題
【令和5年問題】
土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
設問は、正しい。
法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
【令和5年問題】
特定行政庁は、建築基準法第 42 条第2項の規定により幅員 1.8 m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
設問は、正しい。
法第42条第6項より、特定行政庁は、第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
【令和3年問題】
建築基準法第 3 章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員 4 m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
設問は、正しい。
法第42条第2項より、建築基準法第 3 章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員 4 m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
【令和2年問題】
特定行政庁は、建築基準法第 42 条第 2 項の規定により幅員 1.8 m未満の道を指定する場合又は同条第 3 項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
設問は、正しい。
法第42条第6項より、特定行政庁は、第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
【令和2年問題】
道路法による新設の事業計画のある道路で、 2 年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
設問は、正しい。
法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
【令和元年問題】
地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員 5 mの道路法による道路にのみ 10 m接している敷地には、建築物を建築することができない。
設問は、誤っている。
法第42条第1項第一号より、幅員4m以上の道路法による道路は、建築基準法上の道路である。
法第43条第1項より、道路に2m以上接しているため、建築することができる。
【令和元年問題】
土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員 6 mの道路で、 3 年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
設問は、正しい。
法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
【平成30年問題】
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路に該当しない。
設問は、誤っている。
法第42条第1項第三号より、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの道は、建築基準法上の道路に該当する。
【平成30年問題】
土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第3章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
設問は、正しい。
法第42条第1項第五号より、土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第3章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
建築敷地の接道義務

法第43条(敷地等と道路との関係)
接道義務(法43条1項)
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
(接道義務のための道路には、自動車専用道路や高架の道路など自動車の沿道への出入りができない構造のものは除かれる)
接道義務が適用されない建築物(法43条2項)
- 敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し基準に適合するもので、特定行政庁が認めるもの
- 敷地の周囲に広い空地を有する建築物などで、特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
地方公共団体による制限の付加(法43条3項)
地方公共団体は、次の建築物について、道路の幅員、接道長さなどに関して必要な制限を付加することができます。
- 特殊建築物
- 階数が3以上である建築物
- 無窓の居室を有する建築物
- 延べ面積が1,000㎡を超える建築物
- その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く)
接道義務から出題された過去問題
【令和4年問題】
幅員 25mの自動車のみの交通の用に供する道路のみに 6m接している敷地には、原則として、建築物を建築することができない。
設問は、正しい。
法第43条第1項第一号より、自動車のみの交通の用に供する道路にのみ接している敷地には、原則として、建築物を建築することができない。
【平成29年問題】
準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
設問は、正しい。
法第42条第1項第二号より、都市計画法による道路幅員4m以上のものは建築基準法上の道路に該当する。
また、法第43条第1項より、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
接道義務の除外から出題された過去問題
【令和5年問題】
敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
設問は、正しい。
法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に 2 m以上接しなくてもよい。
【令和4年問題】
建築基準法上の道路に該当しない幅員 6mの農道のみに 2m以上接する敷地における、延べ面積 150㎡の一戸建て住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。
設問は、正しい。
法第43条第2項第一号より、その敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。
【令和3年問題】
敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に 2 m以上接しなくてもよい。
設問は、正しい。
法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に 2 m以上接しなくてもよい。
【平成30年問題】
道路に2m以上接していない敷地において、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
設問は、正しい。
法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
地方公共団体による制限の付加から出題された過去問題
【令和3年問題】
地方公共団体は、階数が 3 以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
設問は、正しい。
法第43条第3項第二号より、地方公共団体は、階数が 3 以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
【令和元年問題】
地方公共団体は、特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員等に関して必要な制限を付加することができる。
設問は、正しい。
法第43条第3項より、地方公共団体は、特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
道路内の建築制限

法第44条(道路内の建築制限)
道路内の建築制限は、以下のとおりです。
道路内に建築できないもの
- 建築物
- 敷地を造成するための擁壁
ただし、次に該当する建築物は道路内に建築することができます。
道路内に建築できるもの
- 地盤面下に設ける建築物
- 公衆便所、巡査派出所など公益上必要な建築物で特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
- 地区計画の区域内の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、地区計画の内容に適合し、かつ、政令基準に適合するもので特定行政庁が認めるもの
- 公共用歩廊などで特定行政庁が認めて許可したもの
道路内の建築制限から出題された過去問題
【令和5年問題】
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
設問は、正しい。
法第42条第2項より、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものは、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
法第44条第1項より、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。よって、道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
【令和4年問題】
土地区画整理法による幅員 8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
設問は、正しい。
法第44条第1項のただし書第一号より、地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく、道路内に建築することができる。
【令和4年問題】
公衆便所は、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、道路内に建築することができる。
設問は、正しい。
法第44条第1項のただし書第二号より、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。
【令和2年問題】
道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
設問は、正しい。
法第44条第1項第一号より、道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
【令和元年問題】
地区計画の区域内において、建築基準法第 68 条の7第1 項の規定により特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造することができない。
設問は、正しい。
法第44条第1項より、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
【平成30年問題】
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
設問は、正しい。
法第42条第2項より、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものは、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
法第44条第1項より、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。よって、道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
【平成29年問題】
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
設問は、正しい。
法第44条第1項のただし書第一号より、地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく、道路内に建築することができる。
【平成29年問題】
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員 30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
設問は、誤っている。
法第44条第1項のただし書第二号より、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。特定行政庁の許可を受ける必要があるため、設問は誤っている。
私道の変更又は廃止の制限

法第45条(私道の変更又は廃止の制限)
私道の変更又は廃止によつて、建築敷地の接道義務の規定に抵触する場合は、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができます。
私道の変更又は廃止の制限から出題された過去問題
【平成30年問題】
私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
設問は、正しい。
法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
【平成29年問題】
都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。
設問は、正しい。
法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
位置指定道路の基準
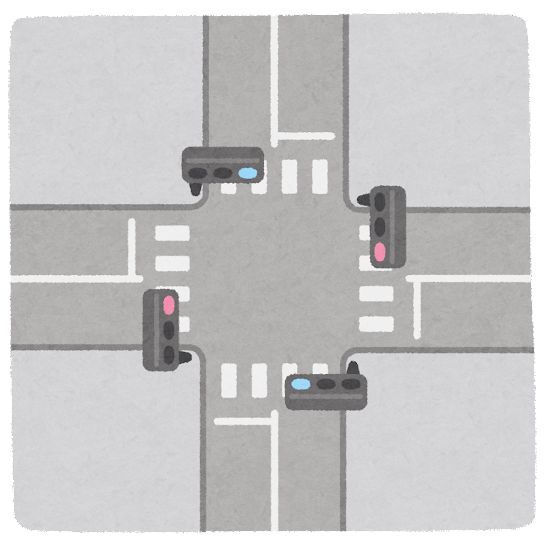
令第144条の4(道に関する基準)
位置指定道路の基準は、次のとおりです。
| 項目 | 基準 | |
|---|---|---|
| 道路の形状 | 原則 | 両端が他の道路に接続したもの |
| 袋路状道路 | 延長が35m以下の場合 | |
| 終端が公園、広場で自動車の転回に支障がないものに接続している場合 | ||
| 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに自動車の転回広場が設けられている場合 | ||
| 幅員が6m以上の場合 | ||
| 特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合 | ||
| 隅切り | 道の交差部、接続部、屈曲部は、辺の長さ2mの二等辺三角形の隅切りを設ける ただし、特定行政庁が認めた場合においては、この限りでない | |
| 道路面の構造 | 砂利敷その他ぬかるみとならない構造 | |
| 道路勾配 | 縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないもの ただし、特定行政庁が認めた場合においては、この限りでない | |
| 排水設備 | 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたもの | |
地方公共団体は、基準を緩和する場合は、あらかじめ、大臣の承認を得なければならない。
位置指定道路の基準から出題された過去問題
【令和5年問題】
土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第144条の4第1項第一号より、袋路状道路を築造する場合、幅員を 6 m以上とするか、終端に自動車の転回広場を設けるかのいずれかでよい。
【令和3年問題】
建築基準法第 42 条第 1 項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を 6 m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
設問は、正しい。
令第144条の4第1項一号ニより、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を 6 m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
【令和2年問題】
土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を 6 m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第144条の4第1項第一号より、袋路状道路を築造する場合、幅員を 6 m以上とするか、終端に自動車の転回広場を設けるかのいずれかでよい。
壁面線の指定と建築制限
壁面線の指定

法第46条(壁面線の指定)
特定行政庁は、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。
壁面線を指定するまでの流れは、以下のとおりです。
- 指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告
- 利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取
- 建築審査会の同意を得て、壁面線を指定
- 指定をした場合は、遅滞なく、その旨を公告
壁面線による建築制限

法第47条(壁面線による建築制限)
壁面線による建築制限は、以下のとおりです。
壁面線を超えて建築してはならないもの
- 建築物の壁、柱
- 高さ2mを超える門、へい
壁面線を超えて建築してよいもの
- 地盤面下の部分
- 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱など
壁面線による建築制限から出題された過去問題
【令和2年問題】
建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
設問は、正しい。
法第47条より、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。屋根は含まれていない。
【令和元年問題】
高さ 2 mを超える門又は塀は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。
設問は、正しい。
法第47条より、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。
仮設建築物に対する制限の緩和

法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)
仮設建築物は、建築基準法の一部の規定の適用が除外されています。
仮設建築物は道路等の規定は適用されません。
- 非常災害用応急仮設建築物(1項)
- 災害時公益的応急仮設建築物(2項)
- 工事用現場事務所(2項)
- 仮設興行場等(5項)
- 特別仮設興行場(6項)
仮設建築物に対する制限の緩和から出題された過去問題
【令和4年問題】
非常災害があった場合において、非常災害区域等(防火地域以外の区域とする。)内に、地方公共団体が、災害救助を目的として、その災害が発生した日から 1 月以内にその工事に着手する応急仮設建築物の敷地は、道路に 2m以上接しなければならない。
設問は、誤っている。
法第85条第1項より、非常災害があった場合において、非常災害区域等(防火地域以外の区域とする。)内に、地方公共団体が、災害救助を目的として、その災害が発生した日から 1 月以内にその工事に着手する応急仮設建築物の敷地は、建築基準法令の規定は、適用しない。
したがって、法第43条の適用はなく、道路に 2 m以上接しなくてもよい。
【令和3年問題】
工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に 2 m以上接しなければならない。
設問は、誤っている。
法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所については、第3章の規定は、適用しない。したがって、法第43条の適用はなく、道路に 2 m以上接しなくてもよい。
問題No.12【道路等】のまとめ
道路等の出題範囲は以下のとおりです。
- 道路の定義と種類(法42条)
- 建築敷地の接道義務(法43条)
- 道路内の建築制限(法44条)
- 私道の変更又は廃止の制限(法45条)
- 壁面線の指定と建築制限(法46条、47条)
- 位置指定道路の基準(令144条の4)
 【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料
二級建築士の試験対策教材はこちらを参考にしてください。
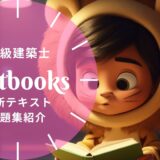 【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説!
【2025年最新】二級建築士おすすめテキスト・問題集を一挙に紹介!教材選びのポイントも解説! 



